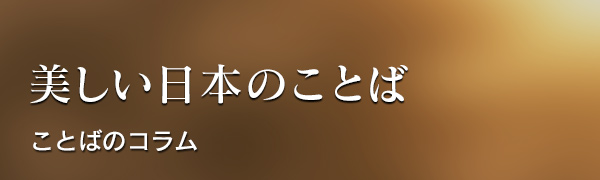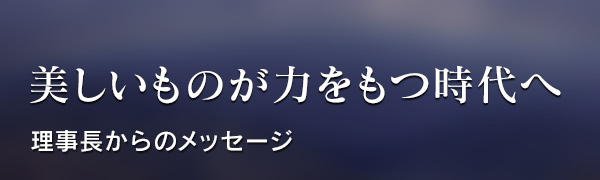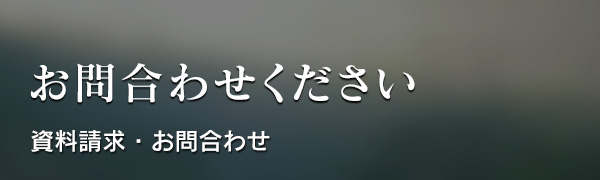悠久の時をガラスに封じ込める
先人たちの思いを未来へつなぐ
ガラス作家
有永浩太
ARINAGA Kota
溶解窯の開発
「sold out」
 パソコンで有永浩太のガラスを取り扱うオンラインサイトを開くと、たいていこの文字が表示される。日常使いのガラスは、モダンでかっこいいと評判。繊細なガーゼシリーズも人気は高い。
パソコンで有永浩太のガラスを取り扱うオンラインサイトを開くと、たいていこの文字が表示される。日常使いのガラスは、モダンでかっこいいと評判。繊細なガーゼシリーズも人気は高い。
「注文はあるんですけど、器は僕一人で作るので、さすがにそんなに数は作れない。2年前の注文を今作っているという状態です」
最初は評判が悪かったガーゼ作品だが、どうやら有永の日本的感覚は間違ってはいなかったようだ。完璧ではなくても、独創的で素材を生かした細やかな仕事に人は魅了される。
「器にしても型を使わないんです。だから、これを作ってって言われても、作れるようになるまでには時間がかかります。最近の展示会で発表しているドット柄の『netz(網)』という作品も、『gaze』から展開したもので8年くらい前から取り組んでいました」
マエストロがオーケストラを束ねる指揮者なら、有永はシンガーソングライターといったところだろうか。ヨーロッパではガラス作りは完全に分業化されており、作家と職人の役割ははっきりしている。ガラス作家は自分のデザインを職人に託し、職人たちは熟練の技を結集する。職人一人ひとりに役割があり、陶芸家のように一人で完結することはない。その伝統あるヨーロッパのガラス技術も年々継承者は減り、マエストロの数も少なくなっているという。日本のガラス業界も例外ではない。
「作家だけで食べている人は少ないと思います。ガラス作家の方でも大学の教員をしたり、どこかの工房に所属している人が多いですし、作っているといってもレンタル工房、一日貸しの工房で創作している人がほとんどですね。やっぱりプロとして一人で生計を立てていけるような人が増えてほしいと思います」
ひとつにはガラス工房にも問題があるという。ガラスを溶かす溶解炉は365日、24時間、火は「つけっぱなし」が常識。一度でも火を消すと、中の坩堝が急冷され割れてしまい、すべて取り替えることになってしまう。ガラス作家は作家であると同時に、火の番人でもあるのだ。外出は許されない。
「そう言われていたので、だったら、そうじゃない窯を自分で作ろうと思いました」
 能登島に拠点を移して、有永がまず取り掛かったのが溶解炉の開発だった。窯の専門家と共同で窯の設計からはじめ、短期間火を止めても同じ坩堝で作り続けることができる、コンパクトな溶解炉を作った。これなら、中の坩堝を取り換えるのも半年に1回程度ですむ。長期間外出するときは、火を消して帰宅後にふたたび点火し温度を上げるだけでいい。ランニングコストもぐんと減る。作家だけでなくガラス職人にとっても画期的で夢のような溶解炉ではないか。
能登島に拠点を移して、有永がまず取り掛かったのが溶解炉の開発だった。窯の専門家と共同で窯の設計からはじめ、短期間火を止めても同じ坩堝で作り続けることができる、コンパクトな溶解炉を作った。これなら、中の坩堝を取り換えるのも半年に1回程度ですむ。長期間外出するときは、火を消して帰宅後にふたたび点火し温度を上げるだけでいい。ランニングコストもぐんと減る。作家だけでなくガラス職人にとっても画期的で夢のような溶解炉ではないか。
「でも、この窯のスタイルって、江戸時代では一般的だったみたいですよ。もともとあったものなのに、なんでなくなったんだろうって思ったんですけど、たぶん明治期に国策として工業化されたものが、そのまま移ったんでしょうね」
かつて使われていたなら今でも使えるはず。そのことに誰も疑問を持たなかったのだろうか。
「それも、趣味でガラスの文献を調べているうちにわかったことなんですよ。江戸時代の絵とか見ると、畳の上でガラスを吹いていたりする。ほんとに小さい窯です。でも、そういうのって僕が小学生くらいのときは、まだ残ってましたけどね」
大阪にひとりだけ、当時と同じスタイルで中空ビーズを作っていた職人がいたそうだ。知る人ぞ知る幻の溶解窯は、考古学者を目指した有永の探究心によって、より進化した新しい姿で復活した。
(写真上下『netz 黒』)
ヴェネチアン・グラスの代表ともいえるレース・グラスの伝統技法をアレンジし、オリジナルの技法で創作するガラス作家の有永浩太さん。布をテーマに展開する作品に『gaze』と名付けたのは、ガラスとの不思議な繋がりがあったからだといいます。透明なガラスの中にはどんなドラマが織り込まているのでしょうか。