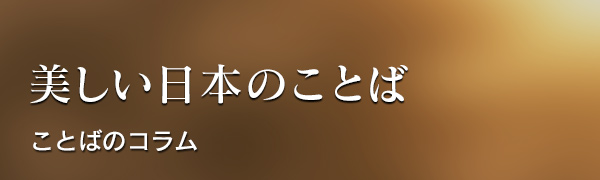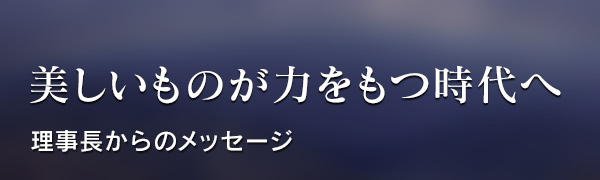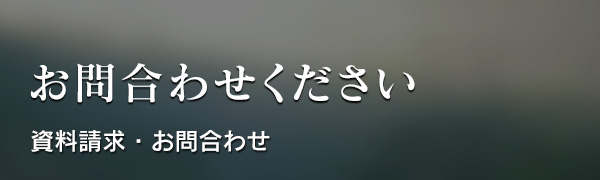山中に育てられたから、山中に恩を返したい
伝統を背負った蒔絵師の新たな挑戦
蒔絵師
松山 武司
Matsuyama Takeshi
職人の町に生まれ育ち、蒔絵職人の父親の背を見て育った松山武司は、父と同じ道を選ぶ。
しかし、同じ道ではあるものの、内容はまったく違う。伝統技術から遠ざかる父に反し、伝統を受け継いでいくことを固く誓う。弟子入りして間もない頃、手渡された一本の筆に伝統の重みを知る。独立後、はじめて伝統を受け継ぐことの大変さを味わい、上には上がいることを知った。伝統を守るとはどういうことなのか。
自分のことのように仲間を、町を、未来を憂う、蒔絵界の若きリーダーの思いに迫る。
山中塗の蒔絵師として
きらきらと煌めく青貝のかけらが散りばめられた万華鏡のような小箱の蓋をあけると、中には無数の星屑が……。
まるで、小宇宙のようなそれは香木を飾り、収める香合。なるほど、小さな香木がひっそりと収まっている。
このオリエンタルな美しい装飾を施したのは山中塗の蒔絵師、松山武司。降り立った小松空港で出迎えてくれたその人は、蒔絵界のリーダーとは思えぬほど控えめで、物腰は柔らかだった。スタイリッシュな装いはクリエイティブ系のビジネスマン風で、一見して職人とは思えない。取材陣のためにわざわざ車で迎えに来てくれたことも、丸2日間、足となり職人たちの工房や町の案内を買って出てくれたことも予想外だった。穏やかで、人の良さが全身から滲み出ていた。
松山の工房兼自宅「T.M Japan Art Studio」に案内されて作業場に入ると、道具類はきちんと整理され、書棚には古書や美術書など貴重な資料が並び、過去の作品の記録もていねいにファイリングされていた。
 作品は伝統工芸の漆器を中心に、細やかな蒔絵が金粉や銀粉を使って繊細に描かれている。一方で、素材に鼈甲を使用したり、バラやアロワナ、ヒョウ柄など、伝統工芸にはあまり見られないモチーフもあった。生木の木目を川と見立て、鳥獣戯画のワンシーンを模写するという斬新な試みや、尾形光琳の『八橋蒔絵螺鈿硯箱』とそっくりの香合を作ってしまうなど、発想は自由奔放だ。
作品は伝統工芸の漆器を中心に、細やかな蒔絵が金粉や銀粉を使って繊細に描かれている。一方で、素材に鼈甲を使用したり、バラやアロワナ、ヒョウ柄など、伝統工芸にはあまり見られないモチーフもあった。生木の木目を川と見立て、鳥獣戯画のワンシーンを模写するという斬新な試みや、尾形光琳の『八橋蒔絵螺鈿硯箱』とそっくりの香合を作ってしまうなど、発想は自由奔放だ。
「人があまりやっていないことをするのが好きなんです。伝統を受け継ぎつつも、ちょっと変わったこともやってみたい」
「山中漆器蒔絵組合」の組合長も務める松山の作品は、同業の職人たちにも定評がある。伝統的な加飾の他、オリエンタルでモダンなデザインは松山ならでは。きらびやかな装飾が人目を惹く。古典的な図柄に抵抗がある人にも受け入れやすいはずだ。
伝統的な技術を踏襲しながらも「少し変わったこと」を常に考えているという松山だが、なぜこの世界に飛び込んだのか、山中塗や蒔絵の魅力は何なのかを、あらためて見つめ直しているという。そうすることで、新しい発想が生まれると思っているからだ。
 松山武司は1962年、石川県江沼郡山中町で生まれ育った。自然豊かで、日本でも有数の温泉郷でもある山中は、松尾芭蕉が『奥の細道』でその湯を讃えていることでも知られている。また、伝統工芸の山中漆器を生んだ町でもあり、木地師をはじめ、塗師や蒔絵師などの職人が数多くいる。
松山武司は1962年、石川県江沼郡山中町で生まれ育った。自然豊かで、日本でも有数の温泉郷でもある山中は、松尾芭蕉が『奥の細道』でその湯を讃えていることでも知られている。また、伝統工芸の山中漆器を生んだ町でもあり、木地師をはじめ、塗師や蒔絵師などの職人が数多くいる。
松山の父もまた、蒔絵を生業としている職人である。その息子が蒔絵師というのは当たり前のような気もするが、蓋を開けてみると、同じ蒔絵師と言えど、二人の方向性はまったく違うものだった。
「父親の世代は、ちょうど高度経済成長のまっただなかで、新しいシルクスクリーン技術を取り入れて量産することが最先端だとされていました。当時は、父だけでなく父と同世代の職人の多くが、量産に走って伝統的な技法から遠ざかっていたようです。漆器なのに本物の漆を使わないとか。それを見て『何か違う』と、ずっと思っていました。どんなに綺麗に仕上がったものを見ても、本物の漆器とは思えませんでした」
職人の町に生まれ、職人として働く父親を見て育った松山ではあったが、どうしても父のやり方に憧れを抱くことはできなかった。松山や同世代の職人たちが伝統に返っていることを鑑みると、伝統工芸を生んだ町の気風が何らかのかたちで働いているとしか思えない。
「はじめから蒔絵師になろうと考えていたわけではなく、美容師を夢見ていたときもありました。ただ、高校3年になって進路を決めるときに、歳をとって美容師をしている自分の姿が想像できなかったんです。それで、蒔絵師になろうと決心しました」
ただし、父とは違う、伝統をベースにした本道を歩いていくことを固く誓った。
高校卒業を3ヶ月前にして、ようやく滑り込みで近所の蒔絵師のもとに弟子入りすることが決まった。兄弟子は二人。職人の師弟関係は厳しいはずで、筆を持てるようになるのは早くても2、3年後だろうと覚悟していた。ところが、
「筆、持ってみる?」と、兄弟子に言われた。
弟子入りして3日と経たずの兄弟子からの思わぬ誘いに肩透かしを食らった。予想しなかった展開で、肩はガチガチに固まり、筆を持つ手が震えた。
「大変なものを目指してしまった」と思ったものの、もうあとには引けない。「伝統」というものの大きさと重みが、筆先からひたひたと伝わってくるのを感じた。