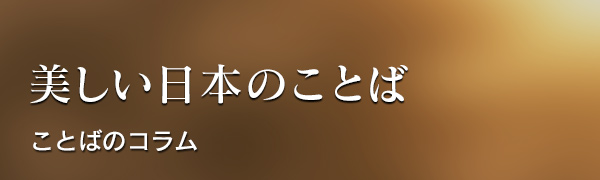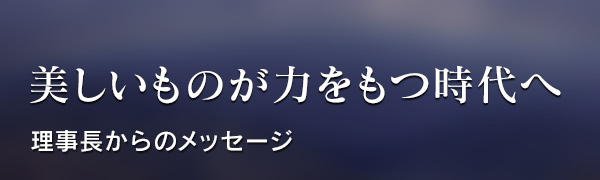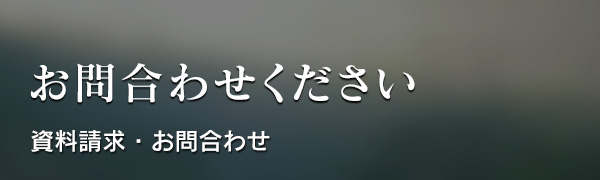引き算の美学
西洋画と訣別して自分らしさを確立する
日本画家
那波多目 功一
Nabatame Kohichi
日本画家として院展に落選し続ける父の姿を見て発奮し、高校2年の時、院展初出品にして初入選という快挙を果たした那波多目功一は、現在の日本画壇において押しも押されもせぬ第一人者として活躍している。
しかし、現在の画風に至るまでは紆余曲折があった。53歳まで会社経営の傍ら、画業を続けたという異色の経歴の持ち主でもある。しかも、はじめの20年は西洋画もどきを描いていた。
「牡丹を描かせたら右に出る者はいない」と言われる那波多目功一の「引き算の美学」に迫る。
日本画と西洋画の狭間で
那波多目功一。押しも押されもせぬ日本画壇の第一人者である。
まったく絵を学ばないまま、ある衝動に突き動かされて院展に応募し、いきなり入選したのが高校2年生の時。翌年は、日展にも初出品で初入選してしまったというデビュー時の稀有な経歴の持ち主は、その後も特異な道を歩み続けた。なんと53歳になるまで、会社経営をしながら画業を続けていたのである。それでいて日本美術院賞(大観賞)3回、文部大臣賞、内閣総理大臣賞など賞歴は目映いばかり。絵を志す者から見れば誰もが羨む才能であるのに、本人はいたって淡々と「絵はあまり好きではないし、いつもやめたいと思っていた」と語る。
日本画でありながら西洋画のエッセンスを巧みに取り入れた20代から40代までの画風から一転、西洋の影響と訣別した後の画風において見事に日本人としての主体性を確立させた。空気や香りなど目に見えないものを描くということ。写実に徹し、それでいて描きたいものだけを抽出し、画布に自分の想念を重ねた。
西洋を経て日本人らしさを獲得した日本画家の神髄を紹介する。
父の仇を討つつもりで絵を描き始めた
悔しい、その思いだけで絵を描いた
 那波多目の父は、日本美術院の重鎮の一人、木村武山や中村岳陵に師事していた那波多目煌星という日本画家。しかし、ほぼ20年にわたって院展で落選の憂き目に遭っていた。
那波多目の父は、日本美術院の重鎮の一人、木村武山や中村岳陵に師事していた那波多目煌星という日本画家。しかし、ほぼ20年にわたって院展で落選の憂き目に遭っていた。
那波多目の生地、茨城県ひたちなか市(当時は那珂湊町)にもう一人いた画家仲間も父と同様、落選続きであった。
二人の関係が変わったのは、その友人が院展に入選してからだ。突如、那波多目の父を見下すようになり、悪口を言い始めたのだ。それを悔しい思いで聞いていた那波多目は、自分が父に代わって入選することで父への罵詈雑言をやめさせようと決意する。当時まだ高校1年生であった。
それまでまったく絵の心得がなかった那波多目だが、そう決心してからの行動は早かった。学校から帰ると自転車で20分くらいの距離にある松林に入り、ひたすら写生を続けた。絵を描いているところを人に見られるのが嫌で、誰にも見られることのない場所を選んだのだ。
「偉い先生方が審査するのだから、絶対に嘘はいけないと思い、ただ見たまま、そのまんまを絵にしました」
そうやって仕上げた作品が右上に掲載した『松山』。その作品を再興第35回院展に出品し、いきなり入選を射止めてしまう。父が20年かけても果たせなかったハードルを軽々と跳び越えてしまったのだ。
「父はとても喜んでくれましたが、内心は複雑だったでしょうね。今度は息子がライバルになってしまったのですから」
それにしても本格的に絵の修業をしていなかった青年はどのようにして絵を描いたのか。
「父の描き方では落選してしまうと考え、自分なりに工夫しましたよ。でも、今考えても大胆な自己流の描き方でしたね。画面の左端側から描き始め、真ん中まで描き終えた時、右半分はまだ真っ白でしたから。脇に写生画を置いて、それを写生しながら仕上げていったのです」と笑う。
快挙はただの偶然ではなかった。翌年、日展に初出品し、これまた入選。ちなみに父が日展に初入選したのは翌年、院展においては11年後である。
「自分らしい絵を描きなさい」
師のひとことが転機に
 「当時、日本画は古くさいと思っていました。どうしてこんなことをやっているのかな、と。かと言って、油絵の粗さも好きではなかったんです」
「当時、日本画は古くさいと思っていました。どうしてこんなことをやっているのかな、と。かと言って、油絵の粗さも好きではなかったんです」
父が選んだ道を踏襲して日本画に進んだものの、日本画の世界に没入したわけではなかった。那波多目が好きな画家はブラック、クリムト、ルオーなど、西洋画の名だたる天才たちであった。彼らの画風を取り入れたり、筆を一切使わずにペインティングナイフで描いたり、新聞紙や布を画布に貼り込むなど、技巧的な試みを続けた。絵の主題は、デビュー当時の写実から離れ、生と死など抽象的な想念の世界に傾いていった。
当時の那波多目には、確固たる自分の画風が定まっていなかったのだ。それに気づかせてくれたのが師匠である松尾敏男のひとことであった。那波多目は昭和47年から松尾に師事していたのであった。
「もっと自分らしい絵を描いたらどうですか。那波多目さんはもっと優しい絵を描けるはずですよ」
松尾が鶴の写生をするのに北海道へ同行した時に言われた言葉だった。西洋の巨匠たちに触発され、思いつくままに何でも取り入れていた弟子に対する忠告であった。「あまり作風が変わるのも良くありませんね。せめて同じスタイルで2年は描き続けたらどうですか」とも言われた。昭和56年、院展初入選後30年、松尾に師事して9年後のことであった。
師のひとことは那波多目の目を覚ますのに十分だった。自分でもそれまでの作風に違和感を覚えていたのだろう。師の言わんとしていることがはっきりとわかった。
その後、那波多目は再び写生に専念するようになる。頭のなかだけで描くのではなく、自然の姿を素直に写し取り、そこに自分の思いを重ねていく。
もう迷いはなかった。友人と一緒に島根県大根島へ赴き、牡丹の写生に取りかかった。松尾は那波多目と牡丹の相性を見抜いていたのか、牡丹を描きなさいと忠告したのである。そのようにして仕上がった作品が、上の『廃園』である。描きたい対象を絞り込んで無駄なものを削ぎ落とし、死生観を込めて描いた渾身の一作はその後の那波多目の方向を変える転機となったのである。