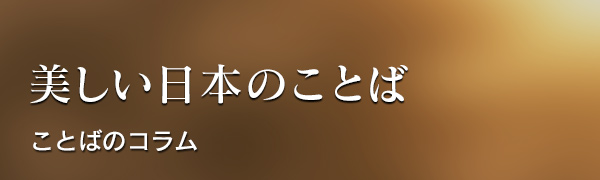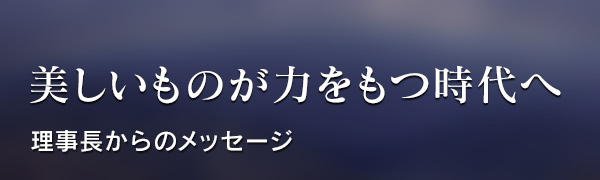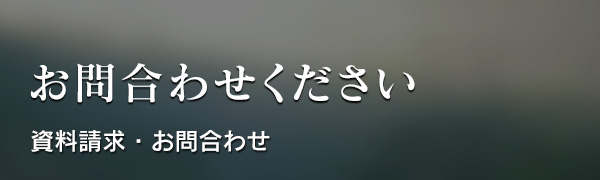山中に育てられたから、山中に恩を返したい
伝統を背負った蒔絵師の新たな挑戦
蒔絵師
松山 武司
Matsuyama Takeshi
伝統と革新を後進へ
 「蒔絵は基本的に、仕上がりまで5つの工程があります。まず、漆で絵を描き、金(銀)粉を蒔き込みます。その後、透漆(すきうるし)といって金粉を固めるために水分を飛ばした漆をその上から塗って固めます。次に、研炭(とぎずみ)で研いで磨き上げる。そして、菜種油と砥粉(とのこ)を合わせたものを布につけてこする。これを胴刷(どうずり)といい、この時にある程度の傷がとれます。胴刷の後、生漆を塗り込んで終了。あとは、早朝、湿気のあるところに半乾きになるまで置いておきます。仕上げに、菜種油を手につけて粉をまぶして手で磨く。すべての工程が終わるまで、簡単なものでも一週間はかかります」
「蒔絵は基本的に、仕上がりまで5つの工程があります。まず、漆で絵を描き、金(銀)粉を蒔き込みます。その後、透漆(すきうるし)といって金粉を固めるために水分を飛ばした漆をその上から塗って固めます。次に、研炭(とぎずみ)で研いで磨き上げる。そして、菜種油と砥粉(とのこ)を合わせたものを布につけてこする。これを胴刷(どうずり)といい、この時にある程度の傷がとれます。胴刷の後、生漆を塗り込んで終了。あとは、早朝、湿気のあるところに半乾きになるまで置いておきます。仕上げに、菜種油を手につけて粉をまぶして手で磨く。すべての工程が終わるまで、簡単なものでも一週間はかかります」
蒔絵の技法は数多く、模様を描いた上に金(銀)粉を蒔く平蒔絵、立体的に盛り上げる高蒔絵、蒔ぼかしや盛り上げを活かして遠近の陰影をつける肉合研出し蒔絵などとさまざまだ。これに、貝や卵殻、金銀の板を貼ったりと、微に入り細を穿った工夫を凝らす。細やかな技術を要すため、手先の器用さはもちろん、湿度に左右される一筋縄ではいかない漆を知り尽くしていなければならない。針ほどの線画をルーペを使って描き終えたかと思えば、乾かし固めて研ぐことを何度も繰り返す。考えただけで気の遠くなるような作業をひたすら続けるのだから、単に絵が上手いだけでできるものではない。センスや技術のほか、根気と忍耐力が不可欠だ。
香合の青貝のかけらは、形を合わせながら一つひとつ貼り付けているという。粉々に砕けたガラスの破片を組み合わせるような途方もない作業を、松山は得意とする。小さな鼈甲のアクセサリーに描かれた絵柄は精密であるにもかかわらず、一筆一筆に迷いがない。古典的な絵柄もモダンな絵柄も、構図は自然で美しい。
「洋書を買いあさってデザインも独学で学びました。その成果が鳥シリーズとエジプトシリーズです」
と言いながら、ファイリングされた作品集の束を懐かしげにめくる。
伝統に育まれ、地域を育む
 駆け出しの頃、名工の作品を見て愕然としたという松山。自分には、とうてい真似はできない。だとしたら、何で勝負できるのか。ひたすらそのことだけを考え続けた。その頃から年に一度、山中塗のコンテストに作品を出品するようになった。テーマは「人がやっていないこと」。技術的なことではなく、新しいデザインと形を追求してきた。
駆け出しの頃、名工の作品を見て愕然としたという松山。自分には、とうてい真似はできない。だとしたら、何で勝負できるのか。ひたすらそのことだけを考え続けた。その頃から年に一度、山中塗のコンテストに作品を出品するようになった。テーマは「人がやっていないこと」。技術的なことではなく、新しいデザインと形を追求してきた。
「人生、一度しかないですからね。一つに絞るのではなく、これもできるけど、こっちもできるというように、いろいろやってみたいと思っています。ただ、最近、パターン化されているな、とも思います。新しい表現方法を開拓しないといけないと感じてはいますが、それもまだ定まっていません」
生計を立てるための仕事と、自分の表現意欲を満たすための創作。それが、どれくらいのバランスで成り立っているかが、職人とアーティストの分かれ目だろう。松山いわく、「自分は職人だから収入には波がある」。依頼仕事を請けるのは、生計を立てるためと割り切っている。それでも、仕事の合間に、できる限り創作を続けていく。そう語る松山の瞳に、アーティストとしてやっていきたいという意欲が浮かんでいた。
松山は、鼈甲と蒔絵の融合やパール粉を使った蒔絵など、これまでも数多くの新しい試みに挑戦してきた。現在は、琥珀や真珠などのジュエリーに蒔絵を描く企画にも取り組んでいる。職人たちの工房へ案内してくれたとき、彼らの一挙手一投足のひとつも見落とすまいと、目を走らせていた。どこかに新しい発見があるのではないか、見たことのない技術があるのではないか。その視線は宝探しをする少年のようにキラキラと輝いていた。
一方で、若手作家や同業者たちの活躍ぶりを自分のことのように誇らしげに語る姿は、蒔絵界の若きリーダーらしい品格を醸していた。
「自分の作品について悩むこともありますが、最近、それと同じくらい頭の中を占めるのが、山中の将来ですね。私は山中塗の歴史と伝統に育てられました。私の人生は山中塗そのものです。この地域の風物が私という人間をつくってくれました。だからこそ、山中の将来を案じないわけにはいかないのです。こんどは私が山中に恩返しをする番です。未熟な私を育ててくれた山中がこれからもずっと繁栄するよう、そして若い作家たちが希望を持ってこの地で漆器に取り組んでいけるよう、組合長として、この町のポテンシャルを高めていくことが使命だと思っています」
 1981年、山中塗は会津塗を抜いて全国一の生産量になった。その伝統を受け継ごうと決めてから長い歳月が流れた。彼はその時の感懐を思い返しながら蒔絵に向かう。
1981年、山中塗は会津塗を抜いて全国一の生産量になった。その伝統を受け継ごうと決めてから長い歳月が流れた。彼はその時の感懐を思い返しながら蒔絵に向かう。
同時に、山中塗に育まれてきた自分がすべきことは、伝統を受け継ぎつつ新しい波を起こしていくことで、山中を活気づけること。それが後に続く若者たちの希望になる。
工芸に限らず、物づくりに携わる多くの人たちは、自分のことだけで汲々としている。松山とて、自分のことで心配がないはずはない。それでも、彼は地域のことを考える。自分のあとに続く者たちの将来を憂えている。自分と同じくらい、人を思いやる。
松山武司が創る蒔絵の世界は、慈しみそのものである。
※作品写真・上から 「香炉」「黒柿借景蒔絵」「寶香箱尾形光琳八橋蒔絵うつし」「高蒔絵香合」「鼈甲ペンダント」「伝統縁起柄オブジェ」「香炉」「真珠に蒔絵柄ジュエリー」
(撮影/山家 学)
(取材・原稿/神谷 真理子)
職人の町に生まれ育ち、蒔絵職人の父親の背を見て育った松山武司は、父と同じ道を選ぶ。
しかし、同じ道ではあるものの、内容はまったく違う。伝統技術から遠ざかる父に反し、伝統を受け継いでいくことを固く誓う。弟子入りして間もない頃、手渡された一本の筆に伝統の重みを知る。独立後、はじめて伝統を受け継ぐことの大変さを味わい、上には上がいることを知った。伝統を守るとはどういうことなのか。
自分のことのように仲間を、町を、未来を憂う、蒔絵界の若きリーダーの思いに迫る。