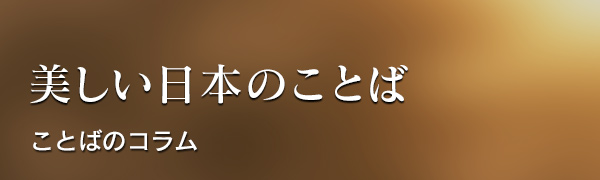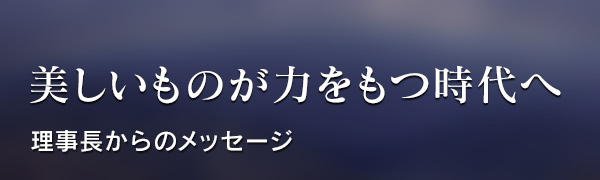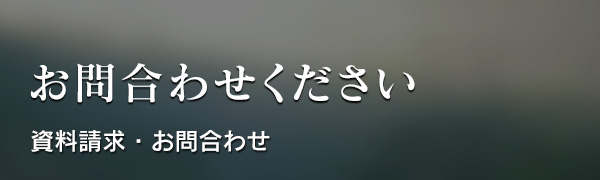悠久の時をガラスに封じ込める
先人たちの思いを未来へつなぐ
ガラス作家
有永浩太
ARINAGA Kota
ガーゼ・グラスの誕生
――日々使うものを日々作る。
大学時代の恩師、小谷眞三氏の教えを守り、有永はひたすら日常使いの器を作り続ける。1年間に何百、何千個。そうやってくり返しくり返し作ることで、ようやく自分の形ができてくる。
「ぱっとは作れないんですよね。思った形を作れるだけの技術を持っていないと作れない。仕事をしながら形は生まれますし、工程はどうしていこうか、どう組み立てていこうかと考えるのも仕事をしながらです」
ガーゼの作品が生まれた時もそうだった。新島での仕事も終わりに近づいた頃、イタリアのマエストロがレース・グラスを披露してくれた事があった。その時に、これまでの色ガラスから進化した、どんなに細く引き伸ばしても色が消えないという新しい色ガラスが開発されたことを初めて知った。
――その素材があれば、編み物や織物のような、ヴェネチアン・グラスとはまったく違うものができるんじゃないか?
有永はさっそく試作に取り掛かった。
「評判は悪かったですね(笑)。これはどう見たってヴェネチアン・グラスではない。もっとそれらしくしたほうがいいんじゃないかと指摘されました」
作り方は伝統的なレース・グラスの手法とほぼ同じ。だが見た目はまったく違う。華麗で寸分の狂いもない完璧なレース・グラスに比べ、有永のガーゼ作品はシンプルかつ独創的なモチーフ。引き伸ばした繊細な織りの網目には〝たわみ〟や〝ゆがみ〟もある。
「イタリアやアメリカで作られるレース・グラスって、日本人の感覚にはちょっと合わないんじゃないかと感じていたんです。完璧すぎるのは、僕としては面白みに欠けると思ったんですよ」
千利休が掃き清められた庭にあえて木葉を散らしたのも、自然に完璧はないということの証明だった。茶碗のゆがみや欠け、アシメトリーな庭に美を見出すのは、日本人の「あるがまま」という自然観のあらわれ。有永は、あくまで素材そのものの面白さを表現し、見る人の想像力を掻き立てようとした。

(写真『『netz 黒』)
ヴェネチアン・グラスの代表ともいえるレース・グラスの伝統技法をアレンジし、オリジナルの技法で創作するガラス作家の有永浩太さん。布をテーマに展開する作品に『gaze』と名付けたのは、ガラスとの不思議な繋がりがあったからだといいます。透明なガラスの中にはどんなドラマが織り込まているのでしょうか。