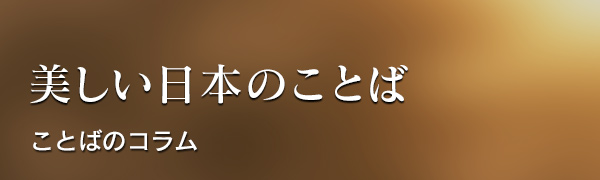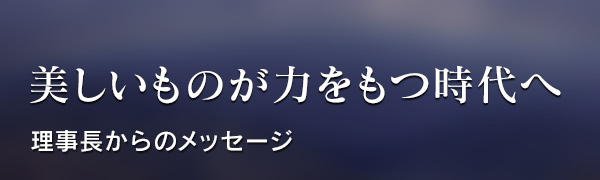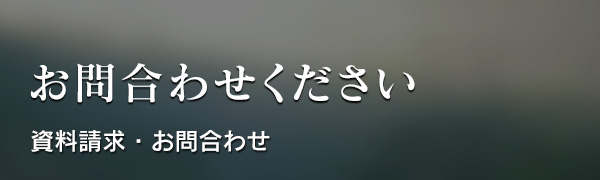世界へ羽ばたく、自由で楽しげな書
命が宿る〝生きている書〟
書家
齋藤 翠恵
SAITO Suikei
空海へのシンパシー
ある日、近所に住む友人に連れられ、書道教室に行った。学生時代に少しかじった程度で、書に格別の思いはなかったが、始めてすぐ、ある手応えを感じた。思いどおりに書けないのだ。
翠恵の奥深いところで眠っていた向上心と好奇心が刺激され、子供の頃に習ったお茶やお華が思い出された。お点前の時、師の美しい所作に見惚れ、どうやったら同じ仕草ができるのかと夢中で真似をしたこと。枝をたわめながら、理想の曲線をつくりたいと没頭したことが蘇ってきた。難しい山ほど、登頂の歓びは大きくなる。翠恵は生涯のテーマを見つけた喜びに浸った。
 テーマが決まれば、努力するのは容易い。要は、その興味が持続するかどうかだ。
テーマが決まれば、努力するのは容易い。要は、その興味が持続するかどうかだ。
書は歴史の長い芸術だが、こと学ぶことにおいては、きわめて恵まれた点がある。それは、偉大な先達が多くの手本を残しているということ。それらを見ながら、古法を学ぶことができる。バッハやベートーヴェンの模範演奏が現代に残っていないことを考慮すれば、その僥倖がどれほどのものか理解できるだろう。
翠恵はすべての書家がするように、王羲之、顔真卿など、さまざまな法帖を手本に稽古を重ねた。
ある日、書道具専門店の本棚に空海の「風信帖」があるのを見つけた。風信帖とは空海が最澄に宛てて書いた手紙で、空海の最高傑作とされ、国宝にも指定されている。
草書体は柳の枝のようにしなやかで、かつ動きは重厚だ。流麗な字の連なりを見ながら本を繰る指に力が入り、戦慄が走るのを感じた。居ても立ってもいられなくなり、それを買い求めた。翠恵と空海のめぐりあいである。
空海の尺牘をむさぼり読むうち、字に潜む魔力にからめとられていくのを感じた。読むほどに深い精神性が伝わってくる。はるか昔に書かれた墨蹟が、時空を超えて現代に生きる自分の心を鷲づかみにする。その関わりの妙に酔いしれた。
「空海は雲の上の人ですから、足元にも及びません。それでも、一歩でも半歩でも近づこうという気持ちで稽古を続けました」
翠恵は生来、〝本物〟が好きだった。生活空間は、できるだけ自分が好きな本物に囲まれていたいと思っていた。そういう人だからこそ、目指す境地をはるか高いところに据えたのにちがいない。
ひたすら稽古に励む日々が続いた。夫と子供を送り出したあと、居間に紙を広げ、臨書に取り組む。寸分たがわず同じように書いているつもりだが、なにかが違う。なぜ違うのか? 見比べて煩悶する。
一心に稽古を続けていると、時の過ぎるのは早い。夕方、子供たちが帰ってくる前に片付け、大急ぎで家事をする。書に出会う前の、のんびりとした日常とは打って変わった。
幸いにして、家族の理解を得ることができた。所属する独立書人団主催の合宿勉強会に参加し、ふだん交わることのない先生に指導してもらう機会を得た。人それぞれに筆使いがある。柔らかく、まったく腰のない羊の毛を自在に操り、思い描く線を書くにはそれ相応の技術が要る。翠恵は、なんとしてもそれらを習得したいと思った。
やがて、それまでできなかったことが少しずつできるようになった。理想の線をイメージし、何十回も試す。自分の進歩はなかなかわからないというが、翠恵は着実に腕を上げていったのである。
動き始める日常
それでも翠恵の日常は、平穏に過ぎていく。変化といえば、ホテル・ニューオータニの書道講座を受け持ってほしいと打診され、教える側になったていどだ。その後、いくつかの書道教室の講師となり、多くの生徒を指導するまでになった。
子供の頃からそうであったように、生活面での不安はない。自分がやりたいと思えば、挑戦できる。それは得難い境遇であり、望んで手に入るわけではない。失礼を承知で書けば、もしそのままの生活が続いていたとしたら、温和だが平板な書家人生となっていただろう。
しかし、ある人との出会いによって、翠恵は大きなうねりのなかに身を投ずることになる。
ある人とは、銀座一穂堂ギャラリーの青野惠子氏。若手作家発掘に情熱を燃やすギャラリストである。翠恵の教え子が青野氏と親しくしていたという縁がつながり、会うことになった。初めての対面だと思っていたが、そうではなかった。
「青野さんにお会いする5年ほど前、ニューヨークのメトロポリタン美術館で日本の織部展が開催された際、私は当時師事していた方について手伝いに行ったのです。そこに偶然、青野さんも茶の道具を提供するためにいらっしゃっていて、私を覚えていてくれたのです」
その後、翠恵は青野さんにいくつかの自作を見せた。もとより、銀座一穂堂で個展ができるとは思っていなかったが、ともに芸術に携わる身、自分の創作を見てほしいと思っていた。
青野さんの芸術を見る目は厳しい。若い時分に書を嗜んでいた彼女は、とりわけ書に対して厳しい目をもち、それまでに多くの書家が作品を携えてギャラリーにやって来たが、すべて断っているということも聞いていた。
ところが、ある日、青野さんから電話があった。銀座一穂堂で個展をやりませんかと。2014年のことである。
それまでに翠恵が催した個展は、05年、銀座松崎画廊での「線の集い」展のみ。心の裡で、快哉を叫んだ。
打ち合わせの際、いくつかの作品を持ってきてほしいと青野から言われていた。そのなかの『國』という作品が、青野さんを魅了する。
「その作品をひと目見るなり、鳥肌がたちました」と青野さん。
じつは、翠恵にとってもその作品は転機となる作品だったのである。
「東日本大震災のあと、連日報道される悲惨な状況を見て、私の意識のなかに初めて覚えた感情がありました。この国、日本のことです。日本を憂えたのです。被害者たちへの思いはもちろんのこと、いったいこの国はどうなってしまうのだろうという思いに衝き動かされました」
強烈な危機感に促されて、翠恵は極太の筆をとり、紙に思いを叩きつけた。黒々と屹立するような、怒気とも慟哭とも感じられる作品が、こうして生まれたのである。
一メートル四方くらいのサイズに万感が込められている。紙から湯煙が立ち上るのではないかと思えるほど、字が生きている。
するすると個展の話は進み、その年(2014年)の10月、開催が決まった。
「個展のテーマはどうしましょう?」
青野さんの質問に対し、すぐに答えられなかった。雑談するうち、空海の書に惹かれて書の世界にのめり込んだ話をした。
「それなら空海をテーマにしましょう。空海に対する想いを表現してください」
青野さんは良いか悪いか、好きか嫌いかも含め、なにごとも即断即決だ。
2回目の打ち合わせの時、翠恵は青野さんの行動力と感性に驚いた。なんと、青野さんは空海展のイメージをつかむため、高知県の室戸岬にある御厨人窟に行ってきたというのだ。
「空海が修行を終えて目を開けたら、目の前にぱーっと空と海が開けていたそうですわ」
御厨人窟で知ったことを語る青野さんの言葉に喚起されて、翠恵の脳裏にひとつのイメージが広がった。どこまでも広がる青黒い海と朝焼けの空。見たわけでもないのに、脳裏にくっきりと映像が浮かび上がった。それを表現するには、二本の筆を同時に用い、青墨と朱墨で描く。
かくして個展を象徴する作品『空海』は生まれた。
「空海を想う」展には、「國」「臥龍沙」など濃墨で書いた骨太の作品、「竹」「申」など淡墨で書いた流麗な作品、「虹」などの絵画的な作品、そして「空海」のような抽象的な作品と、多彩な表現によって翠恵の空海に対する想いが勢揃いした。同ギャラリー始まって以来、最初の書展は大きな反響を呼び、翠恵は新たな境地を拓く端緒についた。

主婦から世界の書家へ、華々しく転成した齋藤翠恵さん。清楚でたおやかな佇まいからは想像もつかない剛健な書は、女性の内面に潜む力強さからくるものだろうか。男手、女手をたくみに使い分け、生きる歓びに満ちた書を書き、新たな世界を切り拓く。