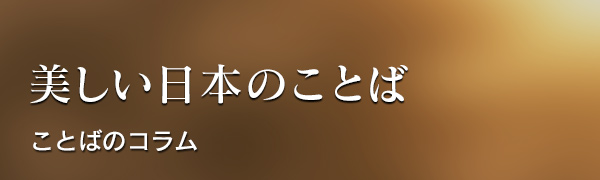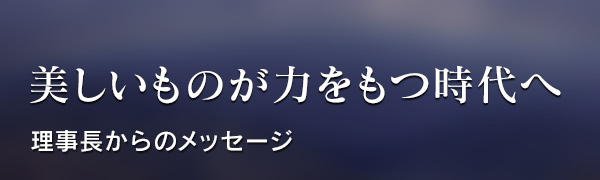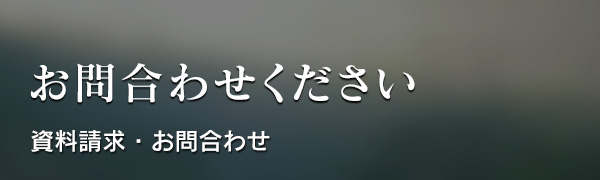巨樹に宇宙を見た男
徹底して現場にこだわる精魄の日本画家
日本画家
石村 雅幸
Ishimura Masayuki
苦悩がくれた自然との邂逅
画家としてのスタート
こうして23歳のとき、初めて師となる人と出会い、画家としての人生が始まった。
翌年、院展に初入選。早咲きだったとも言える。卒業制作で平等院鳳凰堂を描いて以降、石村は日本の古建築を描き続けた。整然と並んだ建造物の瓦、梁や柱にうっすら見える樹の年輪。とにかく細かく、正確に。「ごちゃごちゃしたものを描くのが好き」だというが、徹底した現場主義、写生重視。石村の絵との向き合い方は今も変わらない。森田曠平は彼の資質を見抜き、型にはめることなく個性の成長を見守った。森田は日本画の大家、安田靫彦の系譜に連なるが、小倉遊亀にアドバイスを求められた安田はこう答えた。
――見た感じを逃さぬように心掛けてゆけば(中略)いつの間にか一枚の葉っぱが手に入ります。一枚の葉っぱが手に入れば、宇宙全体が手に入ります――
その安田の言葉のように、石村も目の前の樹と向き合い、すべてを逃さぬようにと我を忘れて写生に取り組む。
石庭を作って壮大な自然を表現するのも、茶室というミニマムな空間に宇宙観や哲学といった普遍性を表現するのも、日本人特有の美意識のもちようだ。一つひとつの写生を大切にしながらも、目に見えない大きな存在を表現しようとするのは、石村の心にそのDNAが刻まれているからだろう。
「もともと建築家にも興味があったこともあって、歴史的建造物の精密な記録になれればいいという思いもありました」
古建築を10年描きつづけたころ、石村の心にある変化が起きていた。院展に連続入選している状況と、出せば入るくらいのものと誤解し始めた周囲の目と、毎回必死でもがいている自分とのギャップにプレッシャーを感じるようになったのだ。できあがった美である古建築。それ以上の美を自身の作品に映し出せないことにもどかしさもあった。画家としての現在の力量を突きつけられる思いだった。
「一度息の根を止めてくれたら、次のテーマに移れると思っていました」
気持ちの入っていない作品だというのは、審査員からすればお見通しである。院展は、日本画を志す人たちが「一生に一度でいいから入選したい」と思う夢の地。そこに人間の業の怖さも感じていた。そして、初入選を果たしてから10年連続入選の後の落選。結婚した年だった。落胆はしたが、なぜか安堵した。
「これでようやく再出発できる」
心のどこかで望んでいた結果だった。あえて落選という道を通らなくても、次のステップを踏める人もいるだろう。しかし、石村は不器用な男である。落選という外からの酷烈な力を借りて、ようやく退路を断つことができた。疲労感と安堵、失意の綯い交ぜになった精神状態の中で、生命力あるものを描きたいという思いが湧いていた。
自然と向き合う画家へ
思えば、いつか樹を主題にしたいと学生のころから資料を集めていたが、志は果たせずじまいだった。茨城県玉造町の大銀杏に出会った時、その「いつか」がやってきた。35歳の冬だった。
「これだ!」と樹に惚れ込んで15号の大きさで写生を描き始めたものの、想像以上のスケールの大きさに圧倒された。
結果、50号へと変更。この作品『樹響精聆』が、巨樹の画家、石村雅幸を誕生させた。
その後の石村の写生は試行錯誤の上、30号から40号の画紙で描かれている。描くときは時間が経つのも忘れて無心になる。
見上げ続けて首がおかしくなったのか、立ち上がったあと倒れて救急車で運ばれたこともあると笑うが、現場への取材はいつも命がけだ。あるときは、崖が崩れて何人もの命が奪われた場所。樹の根を掴んでよじ登り、斜形地でも座れる椅子を現地で自作したこともある。幹の中に藁人形の痕跡を見たこともある。雨の日も大きなパラソルを差して描き続け、車の中で何日も寝泊りすることが常だ。そうまでして巨樹を描き続けるのは、なぜだろう。
「生きているものは、ねじれや揺らぎ、不揃いさがあります。そして、厳しい場所に、上へ上へと枝を伸ばし、命が続いているという事実を見せつけられる。そこに生命の尊さを感じるのです」
描く樹は、事前に1ヶ月ほどかけて入念に調べ上げ、目星をつけて取材に出かける。実際に目の当たりにすると、状況やイメージが違っていることもあるため、さらに何日も理想の樹を求めて車を駆ることもある。ようやく写生を始め、20日間ほどかけて画面と心に刻みつける。
有名な樹や素晴らしい巨樹に出会えればいいかと言えばそうでもない。自分と引き合う樹を探すことが制作の第一歩だ。
「樹のエネルギーが強すぎても怖いんです。こちらの魂が吸い取られそうで」
所詮ちっぽけな人間にとって、自然界の力には敵わない。けれども「何とか対峙できる樹」を探して描くと言う。「苦行僧のようですね」と語りかけると、「そうですね」と笑いながらも、こう答える。
「自分に苦行を強いればいいものが描ける。心のどこかにそういう甘えが出そうになるのですが、そんなに甘くはないんですよね」
時間をかける分、「一瞬のきらめき」のようなものは描けないという石村。流れていく瞬間は描けなくても、何百年、何千年も生きた巨樹が抱える時間の凝縮を、丹精込めて描き上げることができる。それは、巨樹に刻み込まれた自然界の叡智、本質を感じ取ることができるということと等しい。厳しい環境下でおこなわれる巨樹と石村の禅問答。いつか古道も描きたいと思いつつも、巨樹のそばにまだ身を置きたいと考えている。
「これまでは強さとかゴツゴツした父性の強い樹を好んで描いてきました。これからは、巨樹の持つ母性にも視点を置いてみたい」
自然は父のように厳しく、母のようにおおらかである。心を癒してくれた風景が、ある日突然、人間たちに牙を向いてくることもある。
長い時間を生き続け、その両面すべてを知る巨樹は、今日も石村を奮い立たせる。 「巨樹から、ずぶとく生きろって、言われている気がするんです」
石村の作品は、自然の叡智を観る者に伝えるメッセンジャーのようでもある。
樹木と向き合い、宇宙を知る。巨樹に魅せられた画家、石村雅幸。木との禅問答は、まだ続いている。
※作品写真・上から 「長閑」「城門」「精魄」「木魅感慕」「神代桜」
(取材・原稿/関口 暁子 『Japanist』第38号より転載)
20年近く、巨樹ばかりを描き続ける日本画家・石村雅幸。屋外で巨樹に対峙し、1ヶ月近く写生をすることもある。樹の生き様がそのまま露わになったかのようなゴツゴツとした樹肌、大地をしっかりとつかむ生命力みなぎる根……。
石村は、画業の初期から約10年間、古建築を描いていた。しかし、35歳の冬、ある巨樹との邂逅を得、以来、巨樹の本質をあぶり出そうとするかのように巨樹ばかりを脇目もふらず描き続けている。
なぜ彼は巨樹ばかりを描くのか。
巨樹を描くことはどんな意味があるのか。
ひとつのモチーフにとことん取り組む画家の、真摯な生き様に迫る。